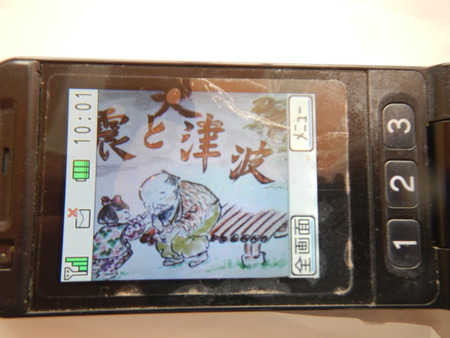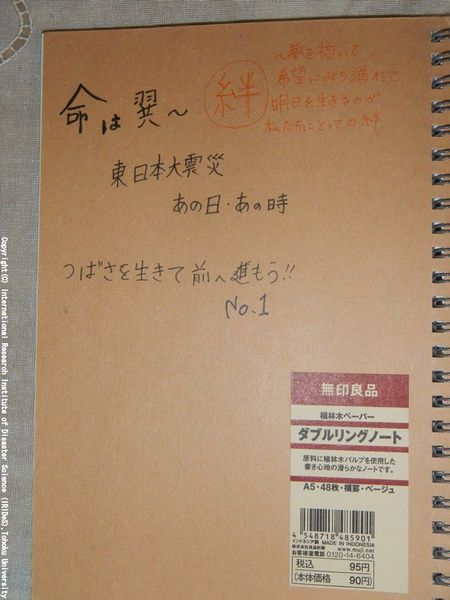0件
- [報告者]
- 政岡伸洋
- [調査者]
- 政岡伸洋
- [補助調査者]
- 岡山卓矢 ・ 遠藤健悟 ・ 大沼知
- [話者]
- (1)Q120(1954年生れ - 男)
海洋青年の家は宿泊施設なので、食べ物などが多少残っていたが、13日からみんなでジュースを拾ったり、津波で流された車からガソリンを集めたり、また食べ物や水の調達をした。水は、最初は沢の水を使っていたが、1週間ぐらいすると津の宮の簡易水道が使えるとわかったのでこれも10日くらい利用し、さらに消防ポンプ車で海洋青年の家の屋上にあるタンクに水をくみ上げるようになると、便所も使えるようになった。電気は1か月以上こなかった。道路は、破損とがれきのため全く使えなかったので、山をまわったり、折立までは船も使った。
海洋青年の家は避難所だったので、自衛隊や役場職員が来るのは早く、震災後1週間ほどで最初の自衛隊のヘリがきた。この頃には自分らでできることはやろうという雰囲気になっていたので、薪拾いや朝のごみ捨て、洗濯、料理などの担当を決めてやった。洗濯は下の沢で、また料理等は女性がやっていた。また、グランドには自分たちが見つけた遺体置き場に使っていた。これらの作業の役割分担については、最初は契約講長が音頭をとっていたが、役場の担当者が来てからは、食事係、食事探しといった役割が分担され、選抜したメンバーで行うようになっていった。ここには300人ぐらい避難していたが、最初は波伝谷の人だけが動いていた。他の部落の人も何人かは来たが、そこに残っている人もいたようなので、それほど多くはなかった。寝る場所は体育館で、毛布もあった。
大部分が波伝谷の人だったので、何事もスムーズにいった。看護師もいて、病人への対応も早く、役場から衛星電話が運ばれ、電話もつながるようになった。
自衛隊より先に米軍が来て、ドラム缶で燃料を支援してくれた。アリーナなどは、人が多くて物資の配分や仕事の分担に手間取ったそうであるが、ここでは早くに体制をつくることができた。流す水はほとんど流されたが、津の宮から向こう側には何軒か家が残っていたので、その頃には海洋青年の家が支援物資の中継所のようになり、話者も、地震後1週間ぐらいから物資分担を担当した。
タグ
関連URL
この話者の他の調査ノート
関連カード
地区
キーワード
みちのく震録伝 -東日本大震災アーカイブ-
宮城県地域文化遺産プロジェクト
ページトップ