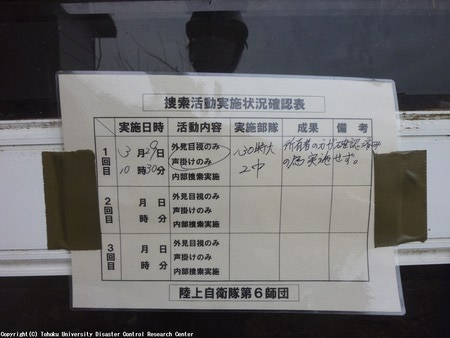0件
- [報告者]
- 林勲男
- [調査者]
- 林勲男
- [補助調査者]
- [話者]
- (1)R124船大工(1928年生れ - 男)
今回の災害前は、造船に執念を燃やす人も周囲に少なくなり、自分も年をとってきたのでしばらく休んでいた。これまでにおよそ300隻の0.5-5トンの木造和船を作ってきた。この津波で、自分の船(0.7トン)が流されてしまった。沿岸のそれぞれの漁協でも多くの船が流されてしまい、すぐには揃わないだろうと考えて、10年ぶりに船づくりに取り組んでみた。
3年ほど前に前立腺癌が見つかり、3ヵ月に1回その検査を受けに病院へ通っている。薬による治療をしており、癌の進行は見られない。自分の船1隻が流されて保険金が30万円おりた。エンジンは外して安全なところに保管していたので被害を受けなかった。新しい船が欲しいが、支援を待っていたのでは、いつ手に入るか分からないので、6月にその保険金で船を作ろうと考えた。それを聞いた奥さんは最初は驚いたが、長男ともう好きなようにさせてあげることにした。病をおしての船造りなので、完成できるか、自分が倒れてしまうかの賭けに出たと思っている。健康には十分に気を付けて、急がずに細く長く働いて完成させた。2か月半で、全長7メートル、幅1.4メートルの船を完成させた。
船造りを始めたことが知られ、川でサケ・マスを捕る川船が流されてしまい、北上川沿いの船大工を探したが見つからないのでということで、依頼が来た。しかし、船は人の財産を預かって作るわけだから、病気を抱える自分が、軽々しく引き受けるわけにはいかないと、当初は断ったが、お盆のころに材料の杉材まで持ち込まれたので引き受けることにした。
櫂は乾燥させたナラの木で作るのだが、津波で使用していた多くの櫂が流されてしまったため、28本ほどあった櫂のすべてに買い手がついた。家や倉庫が流されてしまった人は、売約済みの紙を貼って、うちで預かっている。材料の木は、7、8カ月間から1年間ほど水に漬けておかなければならない。さもないと割れ目が入ったりしやすい。
今後、櫂を欲しいという人が増えてくるだろうから、少しずつ作り置いておこうと思う。
タグ
関連URL
この話者の他の調査ノート
関連カード
地区
キーワード
みちのく震録伝 -東日本大震災アーカイブ-
宮城県地域文化遺産プロジェクト
ページトップ