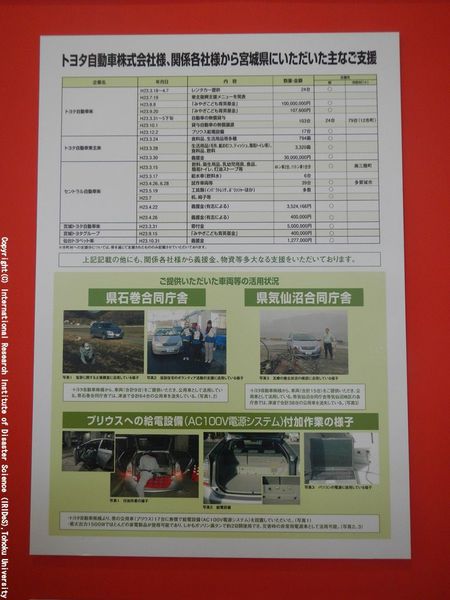0件
- [報告者]
- 梅屋潔
- [調査者]
- 梅屋潔
- [補助調査者]
- 相澤卓郎
- [話者]
- (1)S133浪板虎舞保存会長/鹿折八幡神社氏子総代長/日渡水産社長(水産加工業)(1933年生れ - 男)
虎舞は飯綱神社でまず奉納をして、漁で生計を立てているところを回るものだ。須賀神社は150年ほど前から現在のかたちで崇敬されていたと聞いている。現在の別当はA(屋号は岩城)、渾名は「50番」。タクシーをやっている。飯綱神社の別当は、長浜(屋号)。名字は同じくAである。須賀神社自体は12、3軒の家の共有地であるが、ほとんどそういった意識はない。以前はカトク(家督:家に残ることが期待されている長男)だけが関わっていた。兄が出ていたころには大阪万博で演じたそうだ。前会長のB氏は芸達者だった。前前会長のC氏の代から市に無形文化財指定を働きかけていたが、なかなかうまくいかなかった。平成18年になってようやく指定された。自分が会長になったのは、前会長が退任してから何人か候補が立ったが、あまりうまくまとまらなかった。「日渡しかいない」と推薦するひとがいたが、もともとはカトクでもなかったのでよくわからないし、固辞していた。最後に井戸端が幹事長をして支えてくれるなら、と総会で条件を出した。井戸端が了承したので引き受けることになった。
祭礼の時の会費は1,000円だが、お札が700円で残りの300円で飲食費をまかなう。もともとは「ホウゲ」(宝桶)と呼ばれる桶に入れておにぎりなどを供したものだ。ホウゲは戦後米不足の時期に使われなくなったということだ。主立った家は8軒だが(①鳥越、②岩城、③浦島新屋、④荒屋敷、⑤日渡、⑥日渡の上、⑦高屋敷、⑧木下隣)、そのうち、鳥越、岩城、荒屋敷、日渡の4軒は原則毎回主立った役割を果たす。浦島新屋、日渡の上も準備の中心に加わることもある。岩城と荒屋敷はエンルイである。
従来は、祭典への関わり方にも序列があったが、あるとき平等にしたほうがよいと主張する村人の一人が「ホウゲ」を打ち壊した事件があった。木下隣が仲介しておさめた格好となっている。
浪板1地区は6組に分かれており、かつては3組ずつ交代で役を果たした。現在では人口流出の影響でほぼ4組ずつになっている。多い組は11軒ほどになるが少ないところは5軒しかない。
震災の時、虎の頭のニセモノは蔵にあった。それもぬれたが無事だった。ホンモノは新しい頭を製作依頼していたために八日町のD氏に預けていたので被害を免れた。現在ホンモノは芸能部長が保管している。
タグ
関連URL
この話者の他の調査ノート
- S133浪板虎舞保存会長/鹿折八幡神社氏子総代長/日渡水産社長(水産加工業)
-
2011(PDF)
関連カード
地区
キーワード
みちのく震録伝 -東日本大震災アーカイブ-
宮城県地域文化遺産プロジェクト
ページトップ