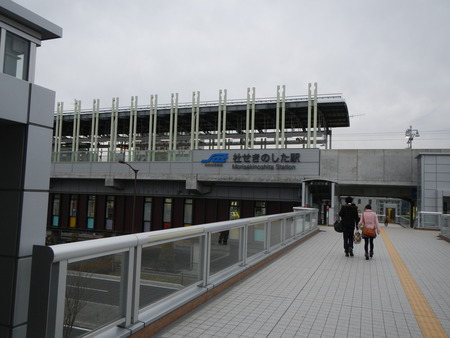0件
- [報告者]
- 菊地暁
- [調査者]
- 菊地暁
- [補助調査者]
- 沼田愛
- [話者]
- (1)G051元警察官(1945年生れ - 男)
現在の家がある場所は、もともと光徳院という寺小屋があった。それに因んでジイサンの戒名にも光徳院を入れている。何かの工事で掘り返した時、湯殿山や月山と書かれた大きな石碑が出て来たが、埋め戻してしまった。
このあたりの地主は鎌田家。現在のフードセンターワダヤの場所に住んでいた。今は余所に住んでいる。ウチの隣のC氏はその分家。名主役を務めていたようで、農家を差配していた。D氏は多賀城町長も務めた。土蔵があるのは、鎌田家と草刈家と馬場家の3軒。とりわけ鎌田家の土蔵は立派で、カギも南京錠ではなくとても大きなものだった。戦後、農地改革で土地をもらった小作人の家が現在も続いている。
この家は2階建て替えている。自分(話者)が生まれた時には茅葺きの平屋で、柱が太くて人が隠れるほどだった。台所と厩が一緒で、入口では鶏を、土間では馬を飼っていた。お化け屋敷みたいで、トノサマガエルでもヤモリでもイモリでも何でもいた。
あたりの家もみな茅葺きで、瓦葺きなのは米屋のF氏の家ぐらいだった。子供の頃に茅葺き屋根の葺き替えを1、2回やった。茅は川沿いに生えていたものや、鳴瀬から運んだものを使った。茅を止める縄を通すために竹串を使うのだが、小さい頃、中からその竹串を受け取る役をさせられ、竹串が目の前にきてびっくりしたことがある。だいたい一週間ぐらいかかり、煤が出て真っ黒になる。
壁は土壁で、藁をきざんでまぜていたので地震でも割れにくい。外まわりの壁は、もともと土壁だったが、よく崩れるので、瓦を入れて作り直した。小さい頃は、屋根を葺くとか壁を塗るとか、職人さんの様子を見たものだ。
板倉は明治の初め頃のもの。籾を貯蔵しており、ネズミ避けがあった。最初は板葺きだったが、大工仕事が好きだった父が瓦に吹き替えた。門は昭和30年の始め頃、仙台から移築したもの。取り壊されるのを惜しんだ父がもらってきて、屋根まわりなども父が補修した。立派な門なので、お寺さんと間違って入ってくる人がいる。
話者家は田畑も多少は持っていたようだ。八幡小学校や八幡神社はほとんど梨畑で、梨を仕入れて売りに行ったとも聞いている。砂押川で泳いでシラウオを獲ることもあり、シラウオはお正月の雑煮に入れた。
小学校4、5年までは乗馬を飼っていた。馬を洗うのは自分(話者)の仕事で、砂押川に入れて洗った馬に背中を見せると鼻をつけるなどのいたずらをする。腹が立ったので鼻の頭の毛を抜いてやった。(高台にある)この家には、水が上がってくるとみんな馬をつなぎに来た。あたりの草を食べさせた。
タグ
関連URL
この話者の他の調査ノート
関連カード
地区
キーワード
みちのく震録伝 -東日本大震災アーカイブ-
宮城県地域文化遺産プロジェクト
ページトップ