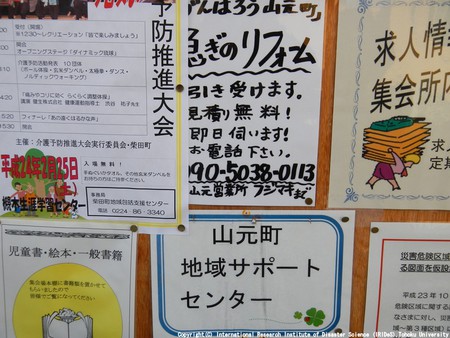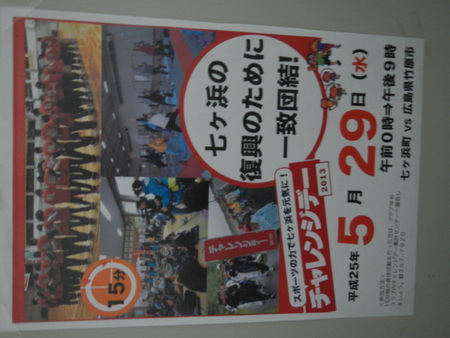チェックリスト
0件
- [報告者]
- 岡田浩樹
- [調査者]
- 岡田浩樹
- [補助調査者]
- 岡山卓矢
- [話者]
- (1)M091大曲浜獅子保存会会長/在宅介護サービス会社代表取締役(生年不明 - 男) (2)M093大曲浜獅子保存会副会長/仮設住宅自治会会長(生年不明 - 男) (3)M092話者①の父/74才(生年不明 - 男) (4)M094矢本在住/齋太郎節歌い手/76才(生年不明 - 男)
昭和40年代には漁業が衰退傾向に向かうとともに、若者は浜の外に働きに行くようになった。とともに、石巻などにつとめに行く者も増えた。このため、漁業暦・村の年中行事と生活の間に乖離が生まれ、1950年代には獅子舞いは次第に停滞、形骸化しかかっていた。ところが第一の大きな転換は、昭和32年の東北博覧会。そこに出ることになり、少しはきちんということで、練習などもしたそれから学校の行事などにも出るようになり、テレビに出演するようになった。この受け皿として愛好会、同好会が大きな役割を果たす。
昭和48年に愛好会が発足。昭和54年に保存会になった。地区住民だけで構成。初代会長は熱海吉郎。会長の父親は3代目の会長。保存会の構成は世代がかなり影響している。70代はかって大曲浜が漁業で栄えた時期の獅子舞を担った世代。その後漁業が低調になっていくにつれて、世代交代がうまく進まず、再び停滞し、その後現在の体制になって再び活動が活発になりかかったところで震災を迎える。
タグ
関連URL
この話者の他の調査ノート
関連カード
地区
キーワード
みちのく震録伝 -東日本大震災アーカイブ-
宮城県地域文化遺産プロジェクト
ページトップ